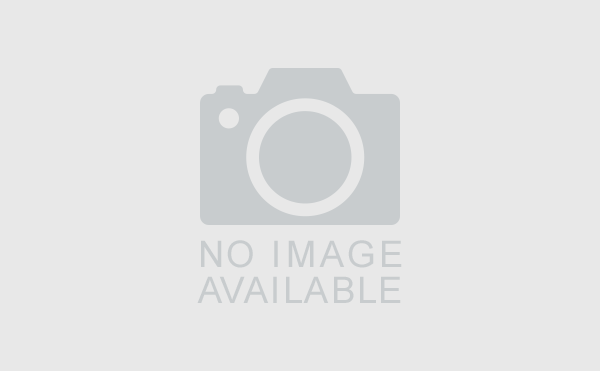障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)
2006年12月13日に国連総会で採択され、2008年5月3日に発効された障害者権利条約ですが、日本では2007年9月28日に署名、2014年2月19日に効力が発生したとされています。
外務省のホームページでは、『障害者権利条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約です。
この条約の主な内容としては、
(1)一般原則(障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容等)
(2)一般的義務(合理的配慮の実施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進すること等)
(3)障害者の権利実現のための措置(身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的権利及び教育、労働等の社会権的権利について締約国がとるべき措置等を規定。社会権的権利の実現については漸進的に達成することを許容)
(4)条約の実施のための仕組み(条約の実施及び監視のための国内の枠
組みの設置。障害者の権利に関する委員会における各締約国からの報告の検討)、となっています。』
条約締結に先立ち,障害当事者の意見も聴きながら,国内法令の整備を推進し、2011年 8月 障害者基本法が改正。2012年 6月 障害者総合支援法が成立。
2013年 6月 障害者差別解消法が成立、障害者雇用促進法が改正。と準備を進めてきたと国は説明をしています。
これを読むと権利や自由に関することは、それが保障されて当たり前とも思える事柄ですが、現実的にはそれが担保されていない課題が昔から問題提起され続けてきたようにも思えます。「施設から地域へ」「社会的入院から地域へ」と少しずつ社会制度も価値観も変化しているようにも思えますが、未だに権利が蹂躙されていることはないでしょうか。例えば、第9条の「安易さ」とはどの程度を「安易」とするのでしょうか。
施策やサービス提供する側からの感覚の「安易」と利用するユーザー側の「安易」には隔たりがあり、立場に関わらず個人でも意識の差があります。加えて、どこまで「安易さ」を実現するかは経済的な影響を背景とする要因もあります。21条の情報の利用は、今回の八王子市の障害者計画への意見でもアクセシビリティコミュニケーションの視点から問題提起されている状況があります。例をあげればきりがありませんが、八王子市内の精神科病院「滝山病院」問題などは象徴的に思えます。精神科の病院も入所施設も本質的には同じで、社会からの隔離的な役割を担っているポジションがあり、それを「必要悪」という片づけ方をする考え方があります。安楽死の承認が臓器移植の問題にもつながり、更には医療費削減という経済的、政治的な合理主義的な解決に向かい、生命の尊厳をわきにしてしまう、まさに大昔の「口
減らし」「姥捨て山」という亡霊が現代にも色濃く息づいている印象です。重度障害者、強度行動障害の方の受け入れ事業者が少ない現状は現状の課題となっています。これは虐待や暴力などの犯罪行為は別ですが、地域の福祉サービス従事者の課題でもあり、予算も含めて施策の問題でもあり、そうした施策(予算配分も含めた)を認める市民である我々一人一人の問題でもあり、そうした課題を私たち一人ひとりが突きつけられている問題でもあります。(文責 有賀)
*以下、日本DPIホームページから国連からの勧
告内容の抜粋がご覧になれます。
https://www.dpi-japan.org/blog/workinggroup/crpd/recommendations-for-japan/