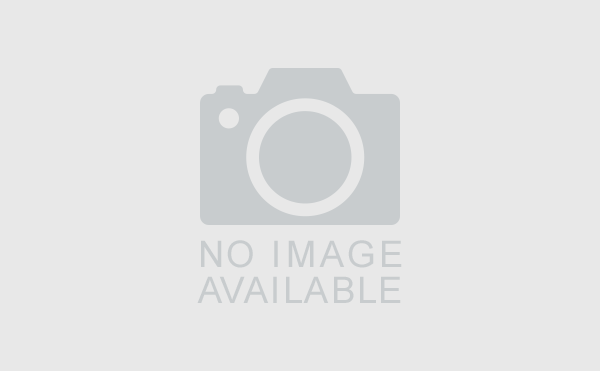連載コラム Vol.74 『インクルーシブ遊具ワークショップ』
八障連代表 杉浦 貢
9月の20日に、市内上柚木公園にて障害のあるお子さんも障害のないお子さんと同じように、一緒に遊べる……『インクルーシブ遊具』の設置に向けたワークショップに出席してきました。
とりあえず私……杉浦の意見としては、『遊具設置だけではインクルージョンな環境は促進しない』ということを発言してまいりました。
日本の保育または教育の分野では、長年に渡り、障害の有無によって子どもさんの育つ環境が分けられていくのが当たり前とされてきました。
いずれ将来は、一つ同じになるにせよ……現時点の社会状況では、まだまだはっきり分けられているのが一般的です。
障害のない子は障害のある子と触れ合う機会がなく、障害のある子もまた障害のない子と触れ合う機会がありません。
そこにただ、遊具だけがあっても、いきなり『みんな楽しくなかよしこよし』な状態が作られるとは、容易には想像しにくいのです。
遊具設置の意味や意義を、まず私たち市民が正しく理解していなければ、せっかく良いものを作っても、宝の持ち腐れになってしまいます
。
遊具設置と同時に、相互理解を目的にした交流、啓発の活動も続ける必要があると思っています。
この日は八障連から代表の杉浦と、運営委員の恒川礼子さん他にも、八王子特別支援学校(PTA)、八王子西特別支援学校(PTA)、八王子東特別支援学校(PTA)、多摩桜の丘学園(PTA)、障害のあるお子さんを支援する親御さんの集まり……きりんさんの会からそれぞれ各団体より1~3名ほどの参加があったようでした。
公園遊具はもちろんのこと障害のあるお子さんが公園で安心して過ごすためには……例えば段差の解消、駐車場の整備、ゆっくり休憩出来る木陰スペース、水道など、様々なものが必要となりますが……ワークショップの場では、広さに余裕のあるだれでもトイレの設置、だれでもトイレへのユニバーサルシートの設置などの意見が出されていたと記憶します。
いずれも、予算とのバランスがあることなので、どこまで実現するかは未定ですが……
⚫公園や遊び場が「インクルーシブ」である意味について遊びは子どもの権利であります、子どもの基本的人権を国際的に保障する「子どもの権利条約」は……1989年に採択され、日本も1994年に批准しています。その第31条に「遊ぶ権利」の条項があり、子どもの年齢に適した遊びをする権利があると記されています。しかし、公共の場でありながら、思うように公園で遊べない子どもたちがいます。それは、障害のある子どもたちです。障害のある子どもたちも含めたすべての子どもたちが公園や遊び場でのびのびと遊ぶためには、あらゆるケースを想定したつくりの公園施設や遊具が必要ですし、共に遊ぶほかのお子さんたちの理解も重要なポイントです。公園や遊び場がインクルーシブになることで、障害の有無にかかわらずに豊かな交流が生まれというメリットがあります。
⚫障がいの有無に関わらず遊べる未来へ
東京都は『「だれもが遊べる児童遊具広場」整備のガイドライン』の中で、現状と課題を次のように触れています。《だれもが遊べる児童遊具広場」は、特別な遊具を設置する広場だと考えられている。そのため、自治体によっては整備に慎重な場合も多い。本来公園はだれでも利用できるものであり、障がいの程度によっては、アクセシビリティ※の改善や保護者等の協力次第で一般の遊具を利用することも可能である。まずは、みんながその特性を理解し、障がいの有無に関わらず、子どもたちが一緒に遊ぶことの大切さを整備計画に反映することが課題となる。》
※アクセシビリティ:近づきやすさ。利用のしやすさも含む。出典:東京都建設局 「だれもが遊べる児童遊具広場」整備のガイドラインについて 「現状と課題」https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/content/000052186.pdf
障がいを持つ人……それぞれの困難さや特性について、この社会で生きる一人ひとりが理解を深め、それを子どもたちにも伝えていくことが大切です。
インクルーシブ遊具をきっかけに、子どもたちが多様な人と共に生きる社会の意義や重要性を認識できるようになるとよいのではないでしょうか。