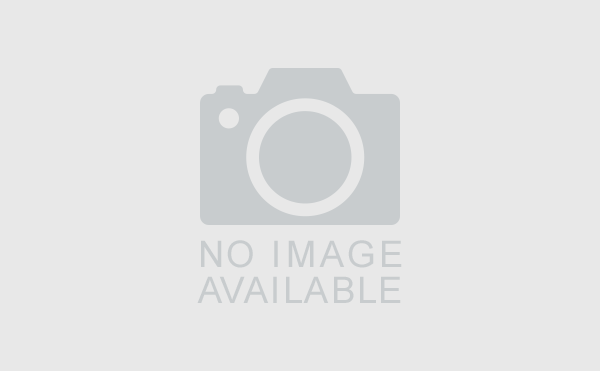映画館での出来事から考える、障害と社会の関係
合理的配慮について考える・・・
2024年4月から障害者差別解消法が改正され、合理的配慮の提供が事業者の義務となります。そのような中、ある映画館で車いすを利用する女性と映画館スタッフの間で起きた出来事が、インターネット上で話題になりました。
この女性は、映画館の通常の車いす席ではなく、座り心地の良い「プレミアムシート」に乗り換えて映画を観たいと希望しました。スタッフの介助によって目的は達成されましたが、後日、映画館の責任者から「スタッフは常に対応できるわけではないので、今後はプレミアムシートの利用を控えてほしい」と伝えられたそうです。

私はこの話を聞き、少し残念に感じました。友人や知人が多く住む調布は、障害のある人にとって比較的便利な街だと聞いていたからです。
この一件の根本的な問題は、映画館の構造そのものにあると私は考えます。「車いすでも映画館に入れるのは当たり前」「どんな席でも自由に選べるのが当たり前」というように、誰もが利用しやすい設計になっていないことが、こうした摩擦を生む原因なのです。
当事者の立場から思うこと
私自身も電動車いすを利用しており、一人で映画館に行くこともよくあります。そのたびに、「一人で行っても大丈夫か」「スタッフに手伝ってもらう必要はないか」といった点を、事前に何度も確認します。まるで「石橋を叩いて渡る」ように、もし入場を断られたり、映画を観られなかったりするかもしれない、という最悪のケースまで想定して出かけるのです。

これは、差別や偏見が今よりもっと厳しかった時代を過ごした私のやり方かもしれません。「自分という存在が、無条件で受け入れられるわけではない」と理解し、あらかじめトラブルを避けるための「予防線」を張っているのです。今回の件のようなプレミアムシートへの移動は、付き添いがいても最初から諦めていることが多いです。
近年、「ユニバーサルデザイン」「インクルーシブ」「バリアフリー」といった言葉が浸透し、障害のある人が特別な心の準備をしなくても、気軽にどこへでも出かけられる社会が求められています。しかし、現実にはまだまだそうなっていないのが現状です。
誤解から生まれる問題
今回の件で、この女性は「以前はスタッフが手伝ってくれたのに、今回は断られた」と主張しています。おそらく、一部のスタッフが個人的な親切心で対応してくれたことを、映画館全体の正式なサービスだと誤解してしまったのでしょう。
私たち障害者にとって、こうした誤解は日常的によくあることです。Aさんというスタッフが親切にしてくれたことが、Bさんという別のスタッフに代わった途端にできなくなる、といった事態は珍しくありません。個人の善意はありがたいものですが、それを当然のことと期待しすぎると、かえってトラブルの原因になりかねません。
今後の改善に向けて
国や自治体のルール、あるいは企業独自のサービス方針に関わらず、すべての対応の基本には、人と人との信頼関係があります。今回の件は、お互いの関係性を築く前に、相手の親切心を期待しすぎてしまったために起きたのではないでしょうか。
「何を、どこまで、どう対応するか」をルールですべて定めるのは非常に難しいことです。しかし、映画館側は「時と場合によっては、対応できないこともある」という点を、もっと明確に伝えるべきです。その上で、二度とこのような問題が起きないように、施設の改善やサービスの向上に努めてほしいと思います。
2024/4/12 八障連代表 杉浦 貢