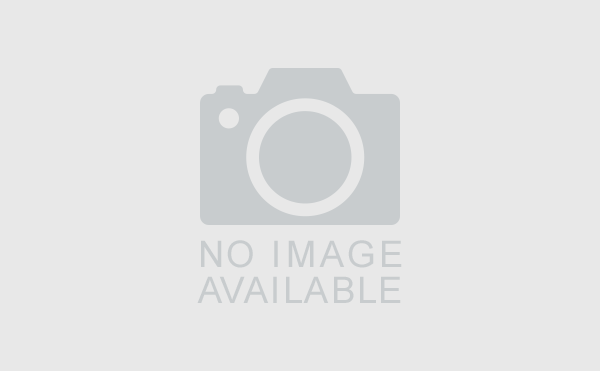八障連通信-416号
八障連通信 416号は、AIを使って執筆をしました。
AIの力も借りて、終戦80年が経過したことも踏まえて、戦争の影響と障害者の人権についておよそ64のサイトや文献をリサーチして、作成しました。
本来は、表なども入って大変わかりやすい記事で小学生や中学生でもわかりやすく読めるように記事作成を行いましたが、ページ数が11ページにも及んだため、4ページにまとめた要約版となりました。
小中学生の方々にも読んでほしい内容でした。短くなったため説明が足りない部分もありますが、基本的人権について今一度立ち返り、障害者の問題を軸とした人権について考えるきっかけになれば幸いです。
障害の理解と人権の基本
はじめに:人権とは 人権とは、誰もが生まれながらに持つ、人間として大切にされるべき「当たり前」の権利です 。
この権利は誰にも侵されることのない永久のものです 。
歴史を振り返ると、奴隷制度のように人権が尊重されなかった時代もあり、多くの人々の努力によって勝ち取られてきた成果であることがわかります 。
日本国憲法でも「基本的人権の尊重」は、国民主権、平和主義と並ぶ3つの基本原理の一つとされています 。
第1章:障害の多様な理解
障害には、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害といった目に見えるものだけでなく、
内部障害、知的障害、精神障害、発達障害など様々な種類があります 。
主な障害の種類と特徴:
- 視覚障害: 全く見えない、または文字がぼやけて見える障害 。
- 聴覚障害: 音を感じたり、会話の聞き取りが難しかったりする障害 。
- 肢体不自由: 病気やケガにより、体の一部または全体に不自由が生じる障害 。
- 内部障害: 内臓や免疫機能が弱まるなど、体の内部に起こる障害 。
- 知的障害: 知的機能の発達に困難があり、日常生活に不自由が生じる障害 。
- 精神障害: 精神機能の障害により、日常生活や社会参加が困難になる障害 。
- 発達障害: 自閉症や学習障害など、脳機能の発達に関係する障害 。
- 高次脳機能障害: 脳の損傷により、思考や言語などの機能に不自由が生じる障害 。
社会モデルという考え方
人権の視点では、「障害」は個人の問題ではなく、社会の側にある「バリア(障壁)」によって生み出されると考えられています 。
これを「社会モデル」と呼びます 。
例えば、車いすの人が階段しかない店に入れない場合、
問題は車いすではなく、エレベーターがないという社会の環境にあるのです 。社会には、建物の構造などの「物理的バリア」、
制度の不備である「制度的バリア」、情報が伝わりにくい「情報的バリア」、
そして、人々の偏見や無理解といった「意識的バリア」が存在します 。
障害のある人の権利と社会的障壁
第2章:守られるべき「当たり前」の権利
国連「障害者の権利に関する条約」 世界では、障害のある人の人権を守るため、国連で「障害者の権利に関する条約」が作られました 。
この条約は、障害のある人を「医療やチャリティーの対象」ではなく「権利を持つ主体」として尊重する考えに基づいています 。
日本も2014年にこの条約を批准し、国内の法律や政策に反映させることを約束しました 。
条約の基本は、無差別、社会への完全な参加、機会の均等などを保障することです 。
「差別されない権利」と「合理的配慮」 障害者差別解消法では、障害を理由にサービス提供を拒否したり、不利な条件をつけたりする「不当な差別的取り扱い」を禁止しています。
例えば、盲導犬の同伴を理由に入店を拒否することは、これにあたります 。
合理的配慮とは、障害のある人から意思が示された際に、過度な負担にならない範囲で必要な対応をすることです 。
具体例として、以下のようなものが挙げられます。
- 車いす利用者のためにスロープを設置する 。
- 筆談や手話でコミュニケーションをとる 。
- 学校で、感覚過敏の生徒のために環境を調整したり、試験時間を延長したりする 。
「地域で暮らす権利」と「働く権利」 障害のある人には、住み慣れた地域で、自分で生活の場を選択しながら暮らす権利があります 。
これを「脱施設化」と呼びます 。
また、自分に合った働き方を選び、社会に参加する「働く権利」も保障されています 。日本では、専用タブレットを使った学習支援や、遠隔操作ロボット「OriHime-D」を活用したカフェなど、多様な働き方が生まれています 。
戦争や災害がもたらす人権の危機
第3章:戦争や災害が奪うもの
戦争による新たな障害と心の傷 戦争は多くの命を奪うだけでなく、新たな障害や深い心の傷を生み出します 。
ウクライナでは、軍事侵攻後1年足らずで13万人以上が新たに障害者になったと推定されています 。
特に地雷や不発弾は深刻で、シリアでは子どもの死傷原因の約3分の1を占め、多くの子どもが生涯にわたる障害を負っています 。
また、過酷な戦闘経験はPTSDなどの精神的な傷を残し、既存の障害を持つ人々はさらに深刻な影響を受けます。
避難生活における困難 紛争時、障害のある人々は置き去り、暴力、死亡のリスクが不均衡に高まります 。
- 情報的バリア: 避難情報が音声や文字のみで提供され、視覚や聴覚に障害のある人には伝わりにくい 。
- 移動のバリア: 空襲警報でエレベーターが停止し、高層階の車いす利用者が避難できなくなる 。
- 生活のバリア: 避難所でのトイレ利用やプライバシー確保が困難であったり、薬や食料が入手しにくかったりする 。特にガザ地区では、多くの障害者がテント生活を強いられ、支援物資へのアクセスも困難な状況です 。
これらの困難は、特に知的障害や精神障害など「外見ではわかりにくい障害」を持つ人々にとって「見えない被害」となり、支援が届きにくい深刻な問題を生んでいます 。
過去の教訓:戦争中の差別と偏見 過去の日本の戦争でも、障害のある人々は深刻な差別に苦しみました 。
沖縄戦では、障害者が「お国のために役に立たない」「穀潰し」などと呼ばれ、スパイと疑われて拷問される悲劇もありました 。
障害のあるジャーナリストの上間祥之介氏は、「災害の時も含めて一番最初に犠牲になるのは立場の弱い障碍者」と語り、当事者の視点で戦争体験を語り継ぐ重要性を訴えています 。
共生社会の実現に向けて
第4章:人権を守り、共生社会を築くために
当事者が社会を変えてきた歴史 障害のある人の権利は、彼ら自身が声を上げ、運動を続けてきた結果として勝ち取られてきました 。
戦後、日本では障害のある人々が差別されながらも、人間らしい生活を求めて立ち上がり、盲学校や聾学校の義務教育化などを実現させま
した 。この歴史は、「私たち抜きに私たちのことを決めるな (Nothing About Us Without Us)」という原則の重要性を示しています 。
国連の「障害者の権利条約」も、長年の当事者
運動の集大成と言えます 。
「誰もが参加できる社会」を目指す国内外の取り組み
- 国際的な取り組み: 国連の「障害者の権利条約」は、紛争や災害時においても障害のある人の保護と安全を確保するよう締約国に義務付けています 。
ユニセフや国境なき医師団(MSF)などの国際機関は、紛争地でのバリアフリー化支援や、心の傷を癒すための心理社会的支援などを行っています 。 - 国内の取り組み: 日本でも障害者差別解消法の改正(2024年4月施行)により、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました 。
東京都では、障害福祉計画を策定し、地域での自立支援やバリアフリー化を進めています 。
私たちにできること 共生社会を築くためには、私たち一人ひとりの理解と行動が不可欠です 。
- 知ること: 障害の多様な個性や、彼らが直面する「バリア」について学ぶ 。
- 意識のバリアフリーを進めること: 偏見をなくし、障害のある人を一人の人間として尊重する 。
- 行動すること: 「何かできることはありますか?」と声をかけ、点字ブロックの上に物を置かないなど、身近な配慮を実践する 。
おわりに 人権という「当たり前」は、過去の多くの人々の努力によって築かれたものであり、今なお脅かされる現実があります 。
特に戦争や災害のような極限状況では、障害のある人々は深刻なバリアに直面します 。
しかし、歴史が示すように、当事者たちの声と行動が社会を変えてきました 。
私たち一人ひとりが社会の「バリア」に気づき、「意識のバリアフリー」を実践することが、未来の共生社会を創るための第一歩となるのです 。