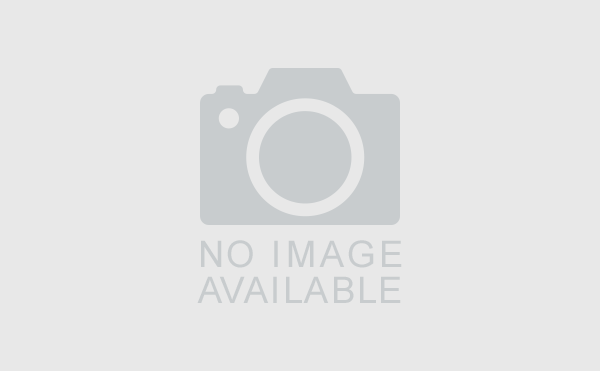連載コラム B型肝炎闘病記 パオ 小濵 義久
手術後の回復は順調で、年末が迫る26日に退院となった。その足で普段世話になっている喫茶店「馬天使」へ挨拶がてら顔を出した後は家で安静にしていた。年が明けた2日は毎年恒例の親戚の顔合わせに出かけた。入院のことは言ってなかったので、普段通り顔を出して癌のことや手術のことは黙っていた。
夕飯時はおせち料理に日本酒。お正月用に少し美味しい地酒を用意してくれていた。はじめて知る銘柄だが、正月にふさわしい美味しい純米酒だった。1ヶ月振りのお酒は身体の隅々まで染み入るようで、手足の指先まで喜び震えているようだ。「それは酔っているだけでしょ!」ってか。5日にはうずうずしてきて、テニスコートへ出かけてしまった。私の姿を見て、みなびっくりしていた。もう戻って来ないのではと考えていた人もいただろうから、驚きもひとしおだったかもしれない。親しくしていた人は、「もうテニスしても大丈夫なの?」と心配して下さった。大丈夫かどうかは身体が一番知っていること。身体と相談しながら、3時間ばかりプレーした。気持ち良かったことと言ったらなかった。テニスも1ヶ月振りだ。
そして高尾山には10日に登り、時々しか行かない薬王院へも廻って初詣でをした。神も仏も信じないのだが、たまにはどの宗派であれ、手を合わすこともある。これもその時々の気持ち次第、身体の動きに任せている。トレッキングも快適で、とても気持ち良かった。なにより汗をかくというのが好きなんなぁだと我ながらつくづく思った。
仕事で汗をかくということは全くないから余計かもしれない。仕事では冷や汗ばかり、脳内は汗だらけかもしれないのだが、、。
25日は虎の門病院の外来だった。普段は3ヶ月に1度の割合なのだが、手術後の経過観察も兼ねて早い外来となった。血液検査の結果に問題はなく、術後の経過は良好だった。「テホノビル」という新しい薬の冊子を私に差し出しながら、ウイルスさえ消えれば癌にはならなくなるのだがと熊田Drが小さく口にした言葉に応えて、癌治療後の絶妙なタイミングだったからか、「やってみましょうか。」という言葉が思わず口をついて出た。
自分の言葉を聞いて、「エーッ、そうだっけか?」と内心では反芻していた。
2000年に「ラミブジン」というB型肝炎に対するはじめての経口抗ウイルス剤が認可され、核酸アナログ製剤が日本でも使えるようになった。恐らく熊田Drからは治験の段階で冊子を渡され、強く薦めはしないがこういうのが出たよと情報はもらっていた記憶がある。ステロイド離脱療法、インターフェロン療法も有効に働かず、1991年から注射をし続けている強力ミノファーゲンC(以下強ミノ)はウイルスを消滅させるような力を持たず、言わば対症療法的な二次的手段にすぎないのだが、新薬に飛びつく気持ちにはなれなかった。
一度使い始めると長期にわたって継続しなければならないということがどこか引っかかったし、私の身体は乗り気の姿勢を示さず、強ミノを打ち続けていれば良いと判断してきた。その後、ウイルスの耐性変異体ができる人もいることが分かり、選択しなかったことにホッとした感じもした。
抗生物質乱用による耐性菌問題が一部では大きな問題ともなっていた。その耐性変異体株を抑制するために2004年に「アデホビル」、2006年には変異株出現率の低い「エンテカビル」、2016年には「テノホビル」が認可された。
次々に新しい薬が開発され、あれこれ考えることもあり、家庭医でもある山田Drとも幾度か話をした。彼の友人の女医さん(私と年齢がそう変わらないか)から同じような質問をされ、「止めておけばと言った。」と仰っていた。ウイルスの消失率は高いのだが、中止後の再燃率が高く、ある意味では一生飲み続けなければならないものと思われる。
たまたまだったのだろうが、強ミノの注射が終了となったその1か月後に3回目の癌治療を行っている。今回の癌(4回目)は9年5ヶ月目だった。
何事も行わず、癌治療を繰り返しながら座してただ死の訪れを待つというのはなんとももどかしい感じもある。肝硬変が軟化する人もいるというのに。強ミノを打ち続けられていれば、選択しなかった治療だろうと思われるのだが、、。